後頭部変形、筋緊張、立てない、歩けない2
続・発語と口周りの変化〜独歩獲得から発語まで
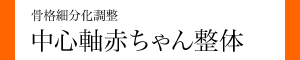 |
東京都江東区 JR総武線【亀戸駅徒歩3分】 営業時間:9:30~15:00 定休日:月曜・金曜 |
発達に関する疑問 |
||
子供の姿勢・頭部変形 |
||
誕生時に頭部変形が無かったのに徐々に変形する場合
誕生時に頭部変形があっても徐々に直っていく場合
マス目の歪みで作られる姿勢
反り返りが異常に強い
首が座らない
書籍案内 |
||
構造的に正しい姿勢
構造的に正しい身体の使い方
<理論編>

<実践編>

中心軸整体・案内 |
||
トップページへ
初めての方・予約方法
料金/営業時間
所在地/地図
検査から調整の流れ
お問い合わせ
整体師プロフィール |
||
骨格細分化調整とは
「マス目の歪み」とは
赤ちゃん整体の雰囲気
よくある質問と回答
リンク
相互リンクはこちらへ
関連サイト |
||
脊柱側湾症・側湾症|中心軸整体
構造的に正しい姿勢|中心軸整体
発達と歪み研究所
ちゅうしん健康日記
ちゅうしん基本食日記
骨格細分化調整師養成セミナー
骨格細分化調整師として
・研究員を目指される方
・独立開業を目指される方
の為に研究員・骨格細分化調整師養成セミナーを開催しています
中心軸整体/実例 |
||
三角頭蓋、クローバーリーフ頭蓋という形を経過して変化
てんかんの赤ちゃん
知的障害 6歳の女の子
知的障害 自閉症 自傷行為 斜視
頭蓋骨変形症、言葉が遅い、よく転ぶ、斜頭
頭蓋骨変形症、言葉が遅い、よく転ぶ、斜頭2
頭蓋骨変形症、言葉が遅い、よく転ぶ、斜頭3
子供整体の10年後、ひきつけ、チック症、斜視、漏斗胸
トゥレット症候群、舟状頭、三角頭蓋
言語遅れ、言語リハビリ、発達障害、舟状頭
言語遅れ、言語リハビリ、発達障害、舟状頭2
上下斜視、調節性内斜視、斜頭
上下斜視 調整性内斜視、斜頭2
発達遅れ 歩行できない アレルギー症状
発達遅れ 歩行できない アレルギー症状2
発達遅れ 歩行できない アレルギー症状3
発達遅れ 歩行できない アレルギー症状4
発達遅れ 歩行できない アレルギー症状5
立てない、歩けない、発達障害、三角頭蓋
発達障害、歪みと食生活
言葉の遅れ、自閉症、多動傾向
ヘルメット治療と骨格細分化調整の並用
頭部の歪み成長への影響、斜頭
膝が痛い
足のしびれ、チック症、三角頭蓋、クローバーリーフ頭蓋
向き癖、頭の形、身体が曲がる(Cの字に)斜頭
運動発達・精神発達の遅れ、頭部の変形、三角頭蓋
発達停滞 てんかん
2歳1ヶ月 歩けない、斜頭、クローバーリーフ頭蓋1
2歳1ヶ月 歩けない、斜頭、クローバーリーフ頭蓋2
トゥレット症候群
猫背 歩けない 先天性両足内反足
猫背 歩けない 先天性両足内反足2
落ち着きが無い 発達障害 言葉がおかしい
落ち着きが無い 発達障害 言葉がおかしい2
姿勢が悪い 脊柱側湾症
斜頸 頭の形がいびつ
ペルテス病 股関節痛
小学4年生 脊柱側湾症
立てない歩けない4才女子1
立てない歩けない4才女子2
立てない歩けない4才女子3
立てない 斜視 1才半、斜頭
2歳になり歩けなくなった、舟状頭
2歳になり歩けなくなった、舟状頭2
2歳になり歩けなくなった、舟状頭3
2歳になり歩けなくなった、舟状頭4
2歳になり歩けなくなった、舟状頭5
転びやすい 左足が内転
自閉症 アトピー 側湾症
発達遅延 歩けない 三角頭蓋、斜頭
発達遅延 歩けない 三角頭蓋、斜頭2
発達遅延 歩けない 三角頭蓋、斜頭3
発達遅延 歩けない 三角頭蓋、斜頭4
呼びかけに無反応 知的遅れ
言葉が遅い 1人で立てない 発達遅延
弱視 斜めにテレビを見る
お座り出来ない 脳性麻痺
お座り ハイハイが出来ない
立てない 発達の遅れ お座りも不安定
言葉の遅れ 首かしげ
頭部変形 将来の不安
1人で立てない 1才8ヶ月
手を離して歩けない 1才8ヶ月
発達停滞 寝返り・ハイハイ出来ない
言葉が遅い つま先立ち
運動機能 自閉症、三角頭蓋、斜頭
運動機能 自閉症、三角頭蓋、斜頭2
内反足 がに股 つまづく
手をつながないと落ち着かない
斜視 おとなしすぎる、舟状頭
歩けない 発語無し 発達遅延、斜頭
多少脳回 歩けない 発達遅滞、小頭症、斜頭1
多少脳回 歩けない 発達遅滞、小頭症、斜頭2
多少脳回 歩けない 発達遅滞、小頭症、斜頭3
多少脳回 歩けない 発達遅滞、小頭症、斜頭4
ダウン症 歩けない、尖頭、尖頭
猫背 チック症状 8才
多少脳回 歩けない 発達遅滞
ハイハイしない 歩けない 座れない、斜頭1
ハイハイしない 歩けない 座れない、斜頭2
中程度知的障害 発達遅延 4才、舟状頭、斜頭 1
中程度知的障害 発達遅延 4才、舟状頭、斜頭 2
手足の緊張 発達遅延 2才、舟状頭
手足の緊張 発達遅延 2才、舟状頭 2
多動 目の動き行動がおかしい 発達障害6才、斜頭
ハイハイ出来ない お座り出来ない1才4ヶ月、三角頭蓋、斜頭
座れない 立てない
情緒の発達と重力ストレスの関係、斜頭
低緊張 立てない 歩けない、斜頭、小頭症
3才で歩けない、斜頭、舟状頭
吃音障害(どもり)・アトピー、斜頭、舟状頭
言葉が1才児位 階段を下れない4才5ヶ月、斜頭、クローバーリーフ頭蓋
夜泣き、向き癖、怖がり 1才
言葉の遅れ 3才6ヶ月、尖頭
三角頭蓋、言葉が遅い、よく転ぶ 2才1
三角頭蓋、言葉が遅い、よく転ぶ 2才2
運動機能全般発達遅延、ずり這いできない、斜頭
立とうとしない、尖足
発達障害、知的遅延、グニャグニャ、扁平足、舟状頭、斜頭、尖頭1
発達障害、知的遅延、グニャグニャ、扁平足、舟状頭、斜頭、尖頭2
受け口、問題行動、肩こり、舟状頭、斜頭
歩行中のふらつき、シャツ噛み、斜頭
右顎・右耳・右股関節痛、片足引きずる、斜頭
長引く咳、斜頭
冷えと風邪薬
姿勢が悪い
子供の姿勢
座り方を注意される
三角頭蓋 ロボットのようなハイハイ
首が座らない 頭部変形-前編
首が座らない 頭部変形-中編
首が座らない 頭部変形-後編
首座りの重要性①
首座りの重要性②
首座りの重要性③
頭部変形変化
多動、偏食、耳ふさぎ、言葉が遅く単語の
不自然に硬すぎる赤ちゃん、生まれた時から緊張していた
ハイハイが異常、立てない1
ハイハイが異常、立てない2
ハイハイが異常、立てない3
頭部の歪みの波及・右膝の痛み
マス目の歪み拡張不足・発達障害と姿勢
グニャグニャしている、走り方が変
御両親の調整、普通に立てる価値
走り方がおかしい、滑舌の悪さ
真っ直ぐ立てない
後頭部変形、筋緊張、立てない、歩けない
後頭部変形、筋緊張、立てない、歩けない2
続・発語と口周りの変化〜独歩獲得から発語まで
低緊張、立てない歩けない〜発達障害 歪みと筋肉状態の影響
便秘 姿勢と呼吸
歪みと顔立ち 小学2年
「発語」につながる口周りの変化 N君 3才